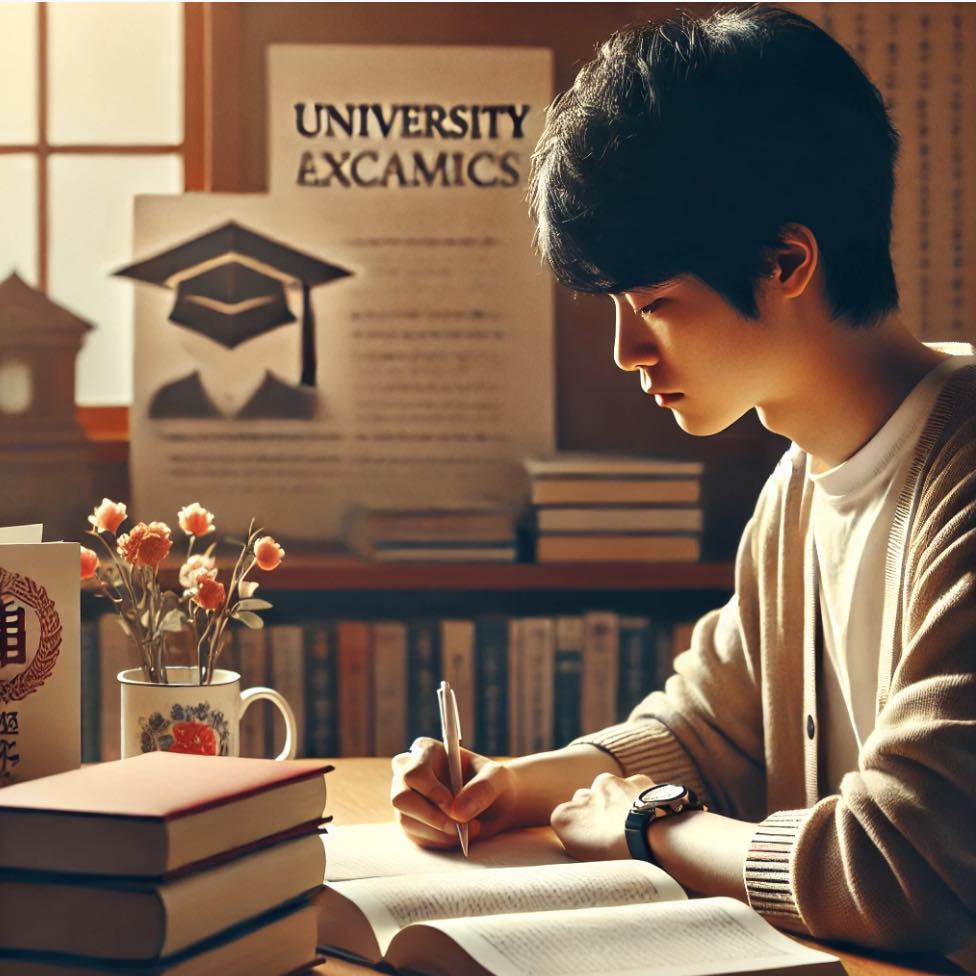これまでの経験談だけでなく、最近のことも書いていこうと思います。今回は、長男の旧帝大合格までの道のりについてお話しします。
塾なしでの挑戦
長男は、今まで一度も塾に通ったことがありません。中学受験も大学受験も、自分なりの方法で勉強し続けてきました。
テスト前になると、塾では過去問を分析して予想問題を作るようですが、長男はそういったものもすべて自力で考え、対策していました。周りのほとんどの子が塾に通う中、何度か「塾に行ってみる?」と聞きましたが、彼は「嫌だ」と即答。どうやら、自分の学習スタイルが塾では実践できないと感じていたようです。
自分のスタイルを貫いた受験生活
中学受験も塾なしで乗り切り、ひたすら過去問を解き続けた結果、合格を勝ち取りました。その成功体験があったからこそ、「自分には塾は必要ない」と思っていたのかもしれません。
ただ、今思えば、高校3年の後半は完全な自学自習では厳しかったのではないかと思います。特に受験本番が近づき、周りの生徒たちが本気モードになってくると、模試の順位が思うように伸びず、少し戸惑っているように見えました。それでも彼は、自分のスタイルを変えることなく、正月まで受験生らしさをあまり見せずに楽しそうに過ごしていました。
他の保護者からは、「うちの子はメンタルが不安定になっていて…」という話も聞きましたが、長男は極端なストレスを抱えることはありませんでした。それが良かったのか悪かったのかはわかりませんが、少なくとも精神的に安定していたのは救いでした。
受験本番と推薦入試
共通テストは、大失敗ではなかったものの、二次試験に十分な貯金ができるほどの点数ではありませんでした。つまり、しっかりと二次試験で得点しなければ合格は厳しい状況でした。
しかし、長男は推薦入試を受けており、一次試験を通過。二次選考の評価と共通テストの結果を合わせた総合評価で、合格の可能性が残されていました。
推薦入試の現状
長男が通っていた高校は、理数科で昔ながらの厳格な指導で有名な学校でした。そのため、一般入試こそ正義、推薦は邪道、という風潮がありました。総合型入試や学校推薦型選抜を受ける生徒は少なく、先生たちも伝統的な一般入試を重視する傾向がありました。
とはいえ、近年では総合型入試の割合が増えてきており、時代に合わせた受験スタイルの変化が求められているのではないかという話もしました。
学校推薦ならわかりますが、総合型選抜を受けるためにも、学校の許可が必要で、教師たちの話し合いが行われるようです。いまだに「真面目な優等生」しか受けさせてもらえなかったようですが、時代錯誤な考え方だと感じました。大学側が評定平均の指定をしていないのに、高校の先生がそれを決めてしまうのはどうかと思います。
実際に、他校に通っていた知人の子どもは、学校の宿題をまったく提出せず、電気工作ばかりしていたそうですが、総合型入試で旧帝大の工学部に合格したそうです。共通テストの得点率は75%ほどだったそうですが、彼の独自の才能が評価された結果だったのでしょう。
長男の最終結果
結局、長男は真面目に自学自習を続けていたことが高評価され、学校推薦型選抜で合格しました。共通テストの点数はギリギリだったのではないかと思います。
しかし、面接では「自分の得意分野について研究したい」という熱意をしっかり伝えたとのこと。好きなことで実績を積んでいたことが、面接の成功につながったのではないでしょうか。
低労力・無課金で旧帝大合格!
長男は最後まで「ガリ勉モード」になることはありませんでした。それでも、自分なりのやり方を貫き、旧帝大合格を勝ち取ったのは、彼自身がこれまで積み上げてきた努力の結果です。
塾なし、低コスト、低労力での合格。本当にすごいことだと思います。